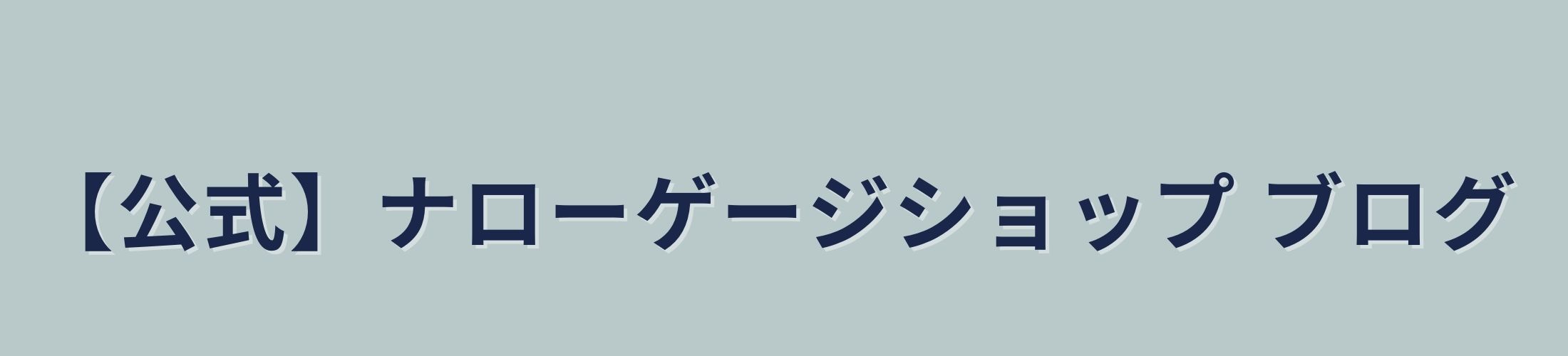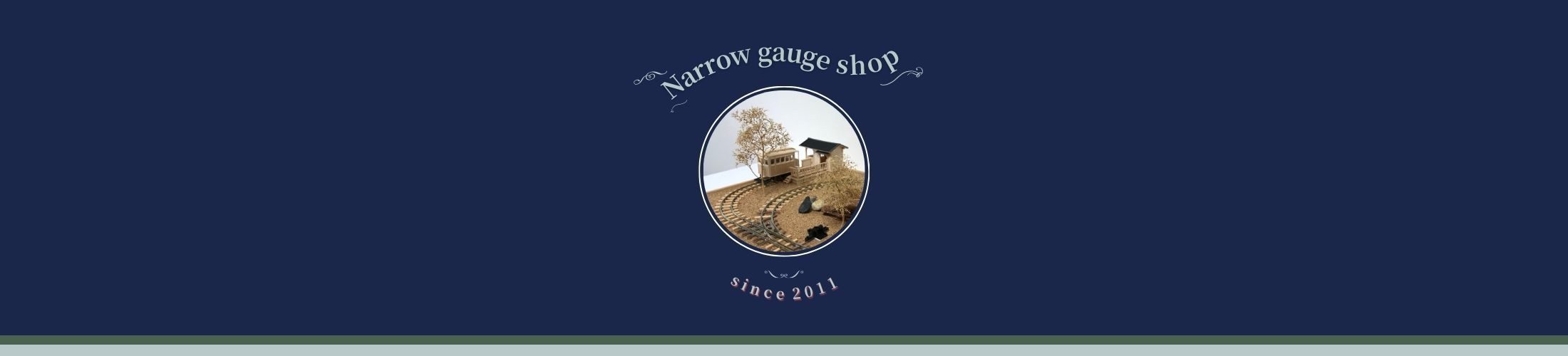PECOの定番ポイントマシンである「PL-10」と「PL-10E」。二つの違いはポイント切り替えロッドの長さです。いったいどちらの製品を使えばいいのか。
ここではレイアウトベース上と下、2つの設置方法を解説します。当店ではPL-10はベース上に、PL-10Eはベース下への設置を推奨しています。
PECOポイントマシンの配線方法については以下の記事を参考にしてください。
関連記事>>PECOポイントマシンの電動化と配線方法のまとめ
関連記事>>トータス?タートイズ?スローアクションポイントマシンの電動化と設置方法
・…━… 目次 …━…・‥
PECOポイントマシン(PL-10)をベース上に設置する方法
使う材料

ここではNゲージ用のポイントレール(SL-E395)と組み合わせて解説します。
PL-10とPL-10EはNゲージからOゲージまで、すべてのポイントレールに対応するパワフルなポイントマシンです。
- PL-10 ポイントマシン
- PL-12(X) アダプターベース
- SL-E395 中型ポイント右
PL-10のスペック

 |  |
 |  |
- 幅:約37mm
- 奥行:約22mm
- 高さ:約23mm(ロッドを含めると約30mm)
- ロッドの長さ:約29mm
まずはPL-10をベース上に設置します。ベース下に設置することも可能ですが、細かい加工が必要になるため初心者の方にはおすすめしません。
重要なのはロッドの長さです。PL-10は本来ベース上への設置が想定されています。ロッドが短いのでベース下に設置するにはポイントレールとポイントマシンを直接組み合わせる必要があります。
PL-10のベース下への設置をおすすめしない理由
 |  |
画像はポイントレールとポイントマシンを直に組み合わせたものです。
間に挟めるとしても1mm~2mmくらいのものになるので、ベースとなるベニヤ他を切り抜く必要があります。
 |  |
参考画像では加工しやすいスタイロを使っていますが、ベニヤを同じように加工するのはひと苦労です。
さらにポイントマシンを設置したあとにバラストを撒くため穴を塞ぐ必要があります。コルクや0.5mm程度のプラ板を間に挟んで塞ぎますがなかなかの作業です。
ベース下に設置する場合には、ロッドが長いPL-10Eを使うことをおすすめします。
- PL-10は基本的にベース上に設置するもの
- ベース下に設置するにはベースの加工が必要
- ベース下に設置したい時はPL-10Eを使うと楽チン!
必須アイテム!PL-12(X) アダプターベース

PL-10をベース上に設置するための必須アイテムが「PL-12(X)アダプターベース」です。
画像にあるのはPL-12とPL-12Xですが、ふたつの違いは中にバネが入っているかどうかです。
PECOのポイントレールにはバネが入っているのでパチンパチンと切り替わります。よってバネが重複しないよう、PECO製にはバネなしのPL-12Xを使います。
ポイントレールにバネが入っていない他メーカー(篠原模型さんなど)のポイントレールを使う場合には、バネありのPL-12を使います。

わかりづらいですが、PL-12は赤丸のところにバネの先端が見えます。
PECOのポイントレールに使う場合はバネを撤去します。
 |  |
裏側の2本の突起を押すとカバーがはずれます。バネを撤去してまたカバーを戻せばPL-12Xと同じになります。
- PL-10をベース上に設置する場合は、PL-12(X)が必須!
- PL-12→PECO以外のポイントレールを使う場合(バネあり)
- PL-12X→PECOのポイントレールを使う場合(バネなし)
- PL-12のバネは簡単に撤去できる
設置方法
① アダプターベースを固定する
 |  |

ポイントレールの位置に合わせてアダプターベース「PL-12(X)」を固定します。
付属の3本のビスで固定しますが、ビスの位置を決めたらピンバイスなどで少しだけ先行穴を作っておくとビスが入りやすくなります。
② PL-10のツメを折り曲げる
 |  |
 |  |
アダプターベースの溝にポイントマシンの突起部を合わせますが、このままでは真ん中のふたつの突起が邪魔になり傾いてしまいます。
アダプターベースと組み合わせる場合には、真ん中の突起を折り曲げてベースに干渉しないようにしてください。
③ ベースに収めれば完成

ポイントマシンの4つの溝とロッドの丸穴を合わせながら乗せたら完成です。難しい加工はなく初めての方でも簡単にできます。
設置場所をポイントレールから離したい場合

通常の使い方だと枕木とアダプターベースの間隔は1cm程度です。
もっと離れた場所に設置して地形の加工などで隠したい場合には同梱されている拡張アームを使います。
 |  |
拡張アームを使えば約6cmくらいまで離すことができます。ただし距離が遠くなるとポイントマシンへの負荷も増えるので極力近い場所に設置します。
PECOのポイントマシン(PL-10E)をベース下に設置する方法
使う材料

- PL-10E ポイントマシン (長軸タイプ)
- PL-9 マウントプレート (PL-10E/10WE用取付板)
- SL-E395 中型ポイント右
PL-10Eのスペック

 |  |
 |  |
- 幅:約37mm
- 奥行:約22mm
- 高さ:約23mm(ロッドを含めると約30mm)
- ロッドの長さ:約57mm
幅や奥行、高さはPL-10と同じですが、大きな違いはロッドの長さです。
ロッドの長さがPL-10の倍近くあります。PL-10をベース下に設置する場合にはベースの加工が必要ですが、PL-10EではPL-9(マウントプレート)を使うことで最小限の加工で設置可能です。
必須アイテム!PL-9 マウントプレート (PL-10E/10WE用)

 |  |
 |  |
- 幅:約47mm
- 奥行:約19mm
- 高さ:約5mm
 |  |  |
PL-10Eをベース下に設置するための必須アイテムがPL-9(マウントプレート)です。
画像左のようにポイントマシンと組み合わせて、プレートの両脇の穴でベース裏にビス留めします。
ロッドはマウントプレートに固定した状態で約25mm出るので、ポイントレールの枕木の厚みを考慮しても、多少厚みのあるベース下にも取り付け可能です。
設置方法
① ロッド用の穴をあける
 |  |
まずはロッドの可動域の穴をあけます。ポイントレールを左右に切り替えて印を付けます。
 |  |
 |  |
マウントプレートの開口部を定規代わりにして、ベースにスミ出しをします。
あける道具は何でも良いですが、私は太めのピンバイスでゴリゴリと削ってしまいます。
② マウントプレートにポイントマシンをセットする
 |  |
プレートの溝に合わせてポイントマシンのツメを差し込みます。差し込んだら6本あるツメをニッパーなどで折り曲げてポイントマシンを固定してください。
③ ベースに固定する
 |  |
マウントプレートの両端をビス留めしてベースに固定します。

ここでひとつ注意ポイントがあります。
付属のビスは長さが約12mmあるので、ベースの厚みによっては表側にビスが突き抜けます。今回使ったベニヤは4mmですが、表側に約5mmほど突き抜けています。
あとからカットすれば問題はありませんが、最初からベニヤに合わせて短いビスを用意した方が手間は減ります。付属のビスはマイナスビスなので、せっかくなので締めやすいプラスビスに変更しましょう。
 |  |
 |  |
④ ロッドをポイントレールに差し込む
 |  |

ロッドをポイントレールに差し込んだら完成です。余ったロッドはカットしてください。
ポイントレールに付けた状態でカットしようとすると余計なところを傷つけてしまう恐れがあるので、スミ付けして一旦はずしてからカットします。
工作ではこのような部分でひと手間かけることで効率も仕上がりも一段上がります。
ベース下に必要なスペース

ポイントマシンがベース下にどれくらい出るかによって台枠の高さなどが変わります。
ロッドの先端まで約32mmです。配線の処理方法にもよりますが、あまり極端に曲げるのはよろしくないので余裕をもって50mmくらい確保したいところです。
- PL-10Eをベース下に設置する場合は、PL-9が必須!
- ベースを厚くしたい場合は、ロッドの長さを考慮する
- 付属のビスを使うと表側に突き抜ける場合がある
- ベース下のスペースは最低でも40mm以上必要!

電動化もせず手動転轍機も使わずに、手元で操作ができる組み立てキットのご紹介です。はんだフリーで組み立ても簡単、コストパフォーマンスにも優れています。
この記事で紹介した商品
以下のリンクよりナローゲージショップの商品ページへ移動します。